中央管理型IDと分散型ID
デジタル社会で個人が生きていくためにはデジタルIDが必須です。そのデジタルIDには中央管理型IDと分散型IDの2種類があります。
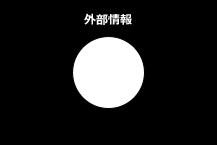
【中央管理型IDのイメージ】
様々な属性(外部情報)で周りを囲んで個人を特定するIDで、クライアント(C)とサーバ(S)の2箇所で共有されます。
情報が変化するとクライアントとサーバで同期しなければならないので更新が必要です。
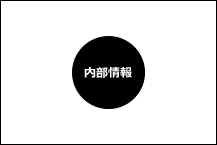
【分散型IDのイメージ】
本人しか知らない記憶の中の情報(内部情報)で個人を特定するIDで、ピア(P)の1箇所に保持されます。
そもそも同期する必要がないので、更新する必要もありません。
上述したように、中央管理型IDは情報の変化に対応して、クライアントとサーバを同期しなければならないので「更新」が必須です。
デジタルIDのメリットは、いつでもどこでもリモートで本人確認して様々な手続きが行える(コンビニで住民票が手に入る等)ことですが、唯一、デジタルIDの更新だけは、本人が役所に出向いて対面して行う必要があります。
というのは、更新中は、IDのいつでもどこでも本人確認できるという機能が停止するため、決められた時間に限られた場所に本人が出向くというアナログ的な本人確認が必要だからです。
上記は、正確にはデジタルIDの中でも中央管理型IDに限られた弱点であり、もう一つのデジタルIDである分散型IDを併用することで、その弱点を補うことができます。
分散型IDは、情報がどことも共有されていないので同期の必要がなく、したがって更新もなく、いつでもどこでも本人確認が可能という機能が停止することはありません。つまり中央管理型IDの更新中も分散型IDを使って本人確認することで、すべての作業がリモートで可能となります。
今後、デジタル社会に移行してからも、中央管理型ID一本では、更新の際に対面での本人確認等アナログ的な作業を続けて行かねばならず、その社会的コストは膨大です。分散型IDを併用することで、そのコストを大幅に削減することができます。分散型IDの代表であるJibangoIDの併用をJibangoは提唱します。(Jibango28510101002538)
氏名のデジタルID化
識別子の定義は「複数の対象から、ある特定の対象を一意的に区別するために用いられる名称、符号、文字列、数値」とあります。ここで重要なのは「一意的」という部分です。
「氏名」は複数の人々の中から、個人を区別する識別子の代表ですが、不完全な識別子です。それは同姓同名があるため、一意に区別できない場合があるからです。デジタル社会では、個人を一意に特定できないと、本人確認や情報伝達がうまく行きません。
そこで現状では「氏名」に生年月日や住所など他の属性(外部情報)を補うことで一意的にして本人確認し、情報伝達を行っています。
しかし、国家規模で本人確認のためのデータベースを構築するとなると、例えば日本の人口は1億2千万人もいて、登録するだけでも膨大なデータ量であるのに、人は移動し、生老病死して情報が刻々と変化するので、それに合わせてデータベースを更新するのは膨大な手間暇(コスト)がかかります。まして人類規模の80億人となると、そのコストは想像を絶します。 これは、デジタル社会のために、アナログのコストを延々と払い続けなければならないという、究極のジレンマです。
そもそもこのジレンマは「氏名」に同姓同名があるという、識別子としての不完全性からくるものです。 そこで「氏名」の同姓同名をなくして完全な識別子にすることが、この問題の根本的な解決策であることがわかります。
では、どうするか。具体的には、現行の「1st+2nd name」の末尾に「3rd name」としてシリアル番号を加えたものを、世界標準の「氏名」として普及させるのです。シリアル番号は重複しないので、それを組み込んだ「氏名」は、対象が一意に決まる完全な識別子になります。 純粋なシリアル番号だと覚えにくいので、シリアル番号を「年月日時分秒」の時刻に変換することで、氏名の部品として認知しやすくしたのがJibangoIDです。 JibangoIDは、一意的にするために住所など他の属性(外部情報)を補う必要はなく、分散型IDなのでデータベースを必要としません。
| 時代 | 伝達媒体 | 氏名の構成 | 同姓同名 |
| 原始 | 音声 | 1st name | 有 |
| 有史 | 紙 | 1st+2nd name | 有 |
| 現代・未来 | 電子 | 1st+2nd+3rd name | 無 |